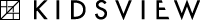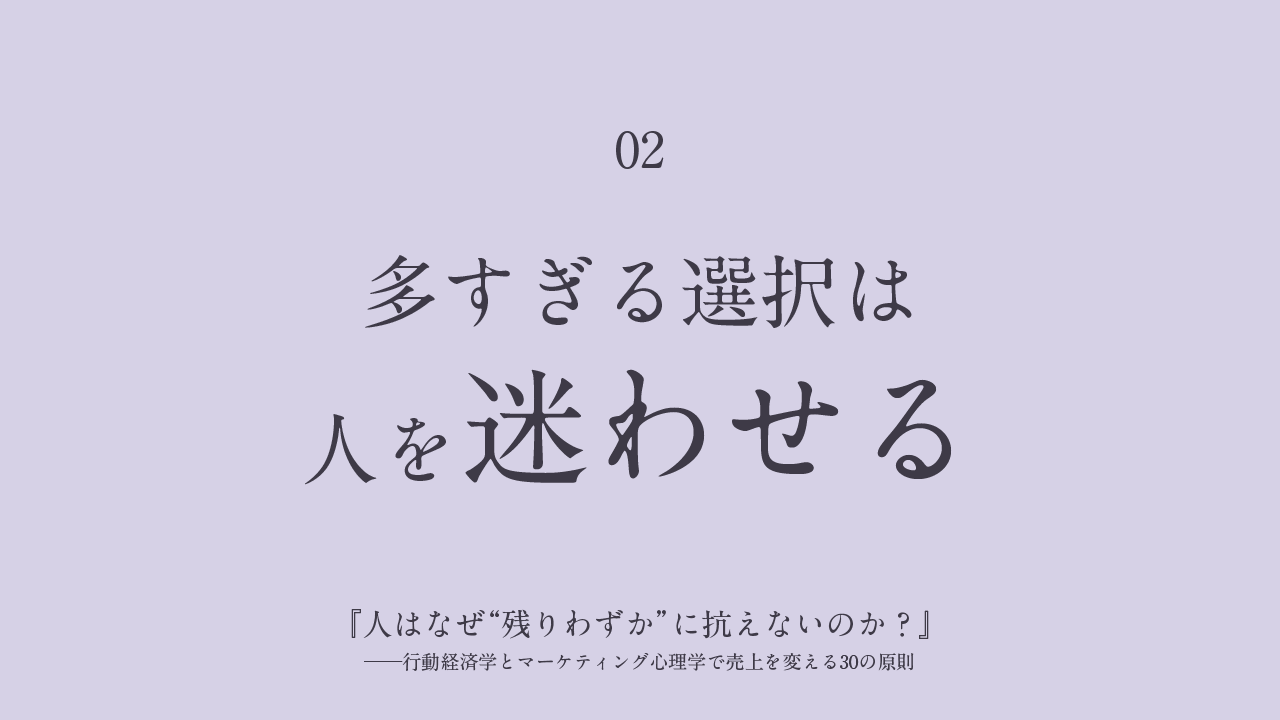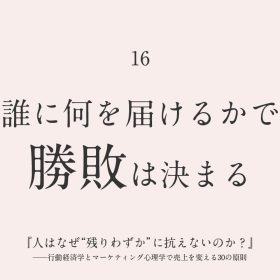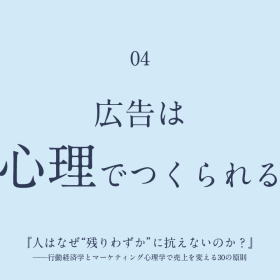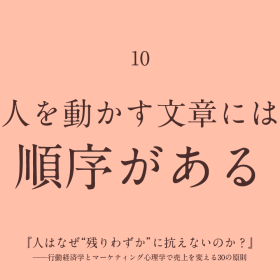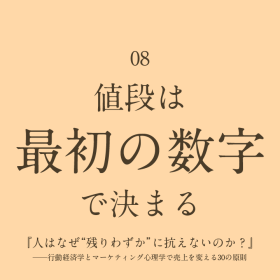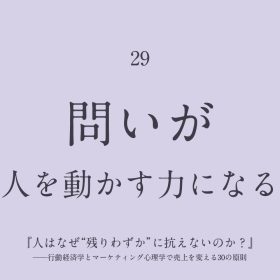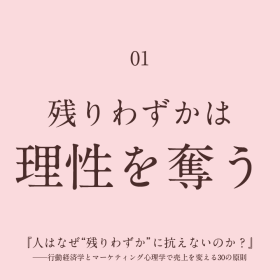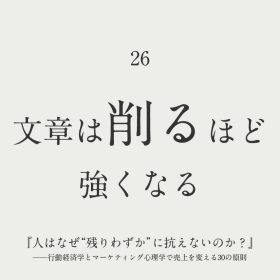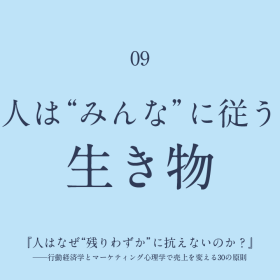「選択肢は多いほど良い」と、私たちはつい考えてしまう。
しかし現実には、選択肢が多すぎると迷い、決められず、結局「買わない」という行動をとってしまう。
これが有名なジャムの法則だ。
理論解説
スタンフォード大学の研究で、24種類のジャムを並べた売り場と、6種類のジャムを並べた売り場を比較した。
・24種類の売り場 → 試食は多いが、購入率は わずか3%
・6種類の売り場 → 試食は少ないが、購入率は 30%
つまり「選択肢が多い=魅力的」ではなく、
選択肢が多い=決断できない=売れない という結果になる。
具体例
・ネットショップで「色やサイズのバリエーション」が多すぎて、ユーザーが離脱する。
・メニューが多すぎるレストランで「結局いつもと同じ定食を頼んでしまう」。
・サブスクのプランが複雑すぎて「後で考えよう」と購買を先送りする。
👉 人は「選べない状態」に追い込まれると、安心安全な「決めない」という行動を取るのだ。
応用
・選択肢は 3~5個に絞る(多すぎると比較疲れを起こす)
・「おすすめ」や「人気No.1」を提示して、選択の軸を与える
・初心者・中級者・上級者の3段階など、分かりやすい階層設計にする
ワーク
あなたの商品・サービスの「選択肢」は多すぎていないだろうか?
・プラン数
・メニュー数
・オプション数
今すぐ一度チェックしてみて、もし10種類以上あるなら 大胆に削る勇気 を持ってみよう。
まとめ
選択肢は「多ければ良い」わけではない。
むしろ人は、選択肢が多いほど決められなくなる。
売れる仕組みを作るなら、シンプルに絞り込み「選びやすさ」を提供することだ。
ここまでが要約した内容です。
本編ではさらに全ての項目を掘り下げ、約7,000〜8,000字のボリュームになっています。
続きは下記のnoteからご覧ください。